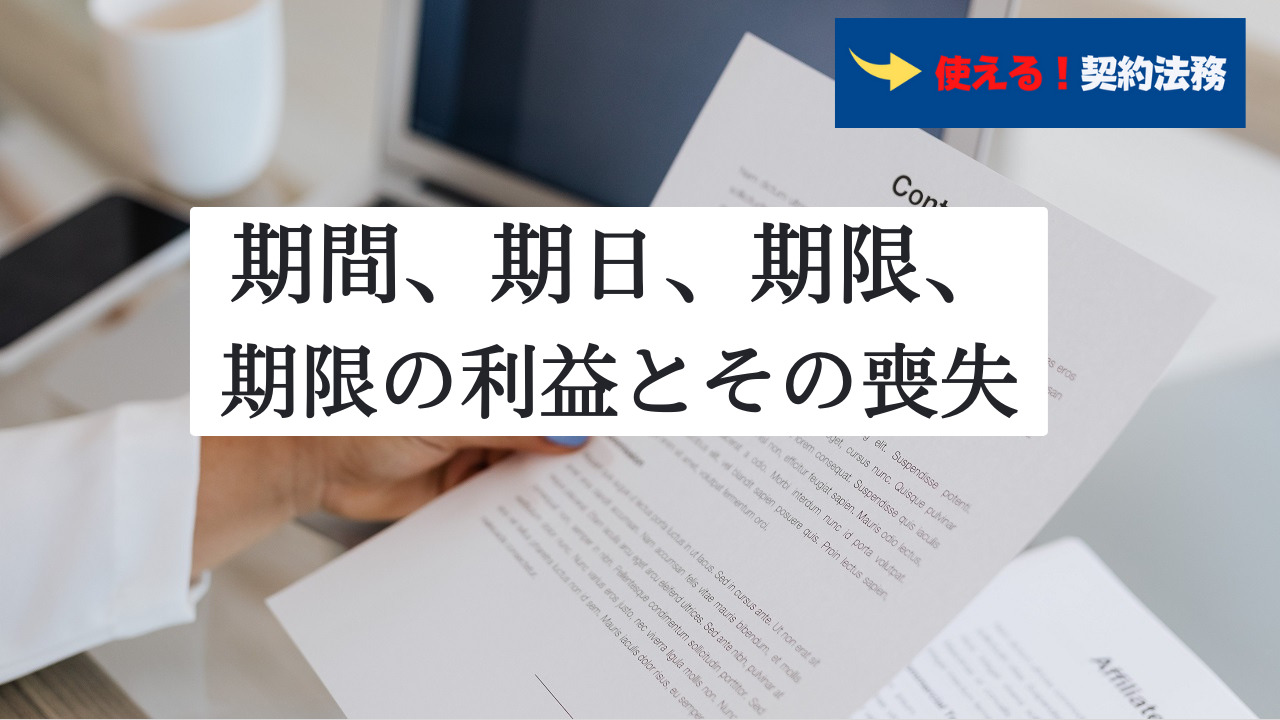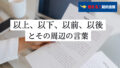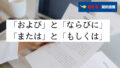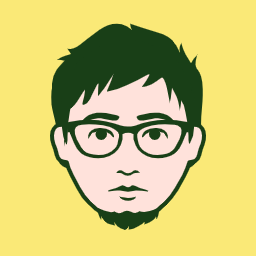
契約書の条項に「期限の利益喪失」というのがあるが。ちょっと意味わかりませんわ。

「期限の利益喪失」って確かに契約書に馴染みがない人にとっては奇妙な言葉ですね。
後で説明しますが、「あーそんなことか」と納得頂けると思います。
期間
「期間」とは、日にち等を指定する表現のうち最初と最後の双方を指定するものをいいます。例えば、「2022年10月1日から2022年10月31日までに代金を支払う」
「納入が完了したときから6カ月以内に代金を支払う」
というものがこれにあたります。
期間の計算方法
- 時間の起算点
即時に起算します。
例えば「午後1時から1時間」といえば、午後2時00分で期間が満了します。 - 日の起算点
初日が完全に1日ある場合を除いて初日は算入しません。
例えば4月15日に「今日から5日間」といえば、通常既にその時点では4月15日は丸一日ないので、4月16日から起算して5日間、即ち4月20日の24時で期間が満了します。 - 日は暦による
例えば4月1日に「今日から1年間」といえば、翌年の4月1日の24時00分で期間が満了し、うるう年でも関係はありません。
また8月1日に「今日から1カ月」といえば、9月1日の24時で期間が満了し、1カ月が30日か31日かは関係がありません。
期日
「期日」とは、日にち等を指定する表現のうち特定の日を指定するものをいいます。
例えば、「支払いの期日は2023年4月1日とする」とすれば2023年3月31日に支払っても正しく履行したことにはなりません。2023年4月1日まさにその日の24時間の中で支払わなければなりません。
期限
「期限」とは、日にち等を指定する表現のうち初めまたは終わりの一方のみを指定するもので、始期以後または終期以前における不定の時間的な広がりのあるものであり、「期日」とは異なります。
例えば、「支払いの期限は2023年4月1日とする」とすれば、現在から2023年4月1日までの間に支払えば正しく履行したことになります。
銀行振り込みで支払う場合、支払い期限の日が銀行休業日にあたれば、履行したくても履行できません。
このような場合は、「支払い期限の日が銀行休業日の場合、直後の銀行営業日を支払い期限とする。」といった但し書きを合意して疑義をなくすことが望ましいです。
期限の利益、期限の利益喪失
「期限の利益」とは、期限がまだ到来しないことによって受ける利益を言います。
といっても、よくわからないですよね。
法律上の原則としては、例えば売買の場合、物の引渡と代金の支払は同時に行うことになっています。しかし、物の引渡時期よりも代金の支払時期を後にしている取引の方が実務上多いです。
例えば、2023年1月10日に物品が納入された後、「代金支払いの期限は、2023年3月31日とする」という場合、2023年4月1日以前に支払うことを相手方から請求されても拒むことができることになり、これが「期限の利益」にあたります。
期限の利益喪失というのは、期限の利益を強制的に喪失させる効果を言います。多くは、債務者の経営不安が明らかになったときに喪失させるとしています。
例えは、上の例でいうと、支払うべき者が、2023年3月5日に銀行不渡りを出した場合、2023年3月31日を待たず直ちに代金支払いを行うよう要求することになります。
3月31日まで待つと回収できないリスクが高まるという理由で「期限の利益喪失条項」が入っています。